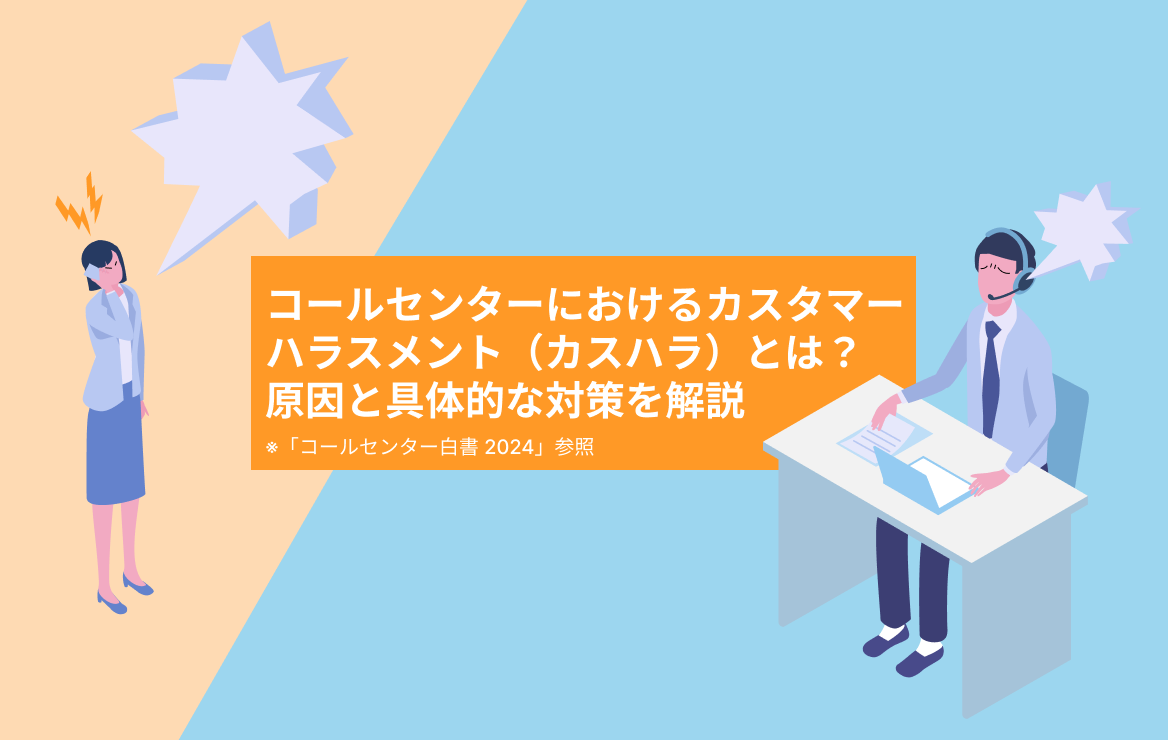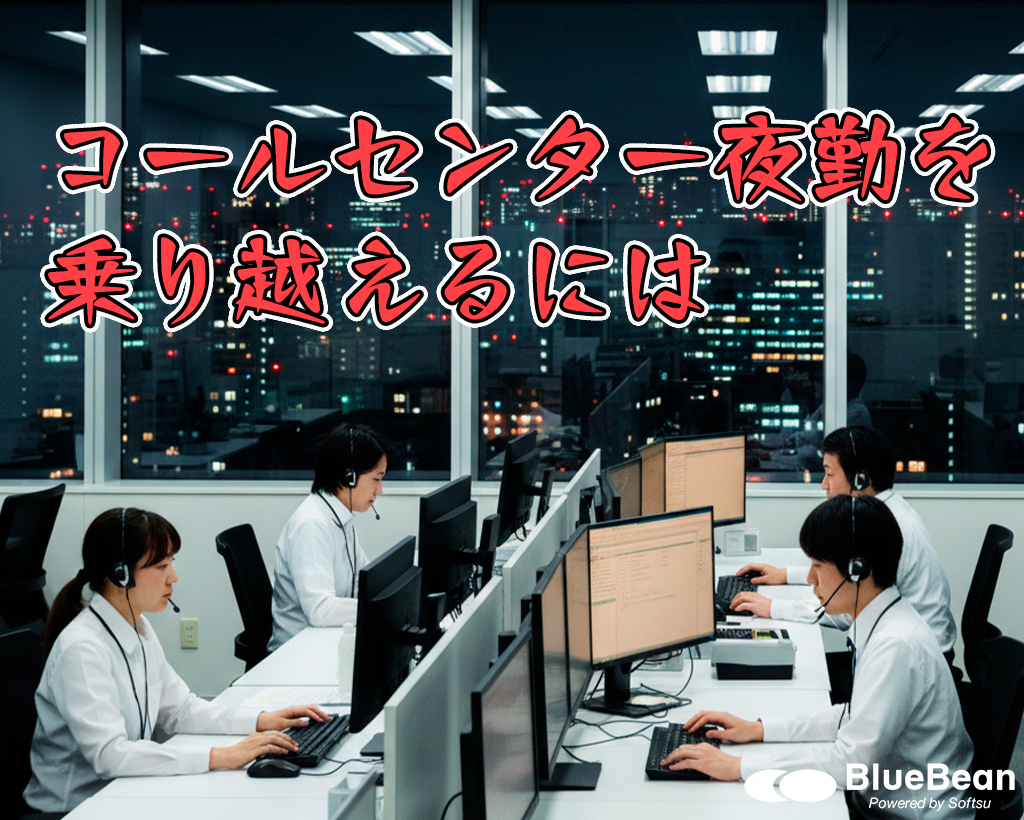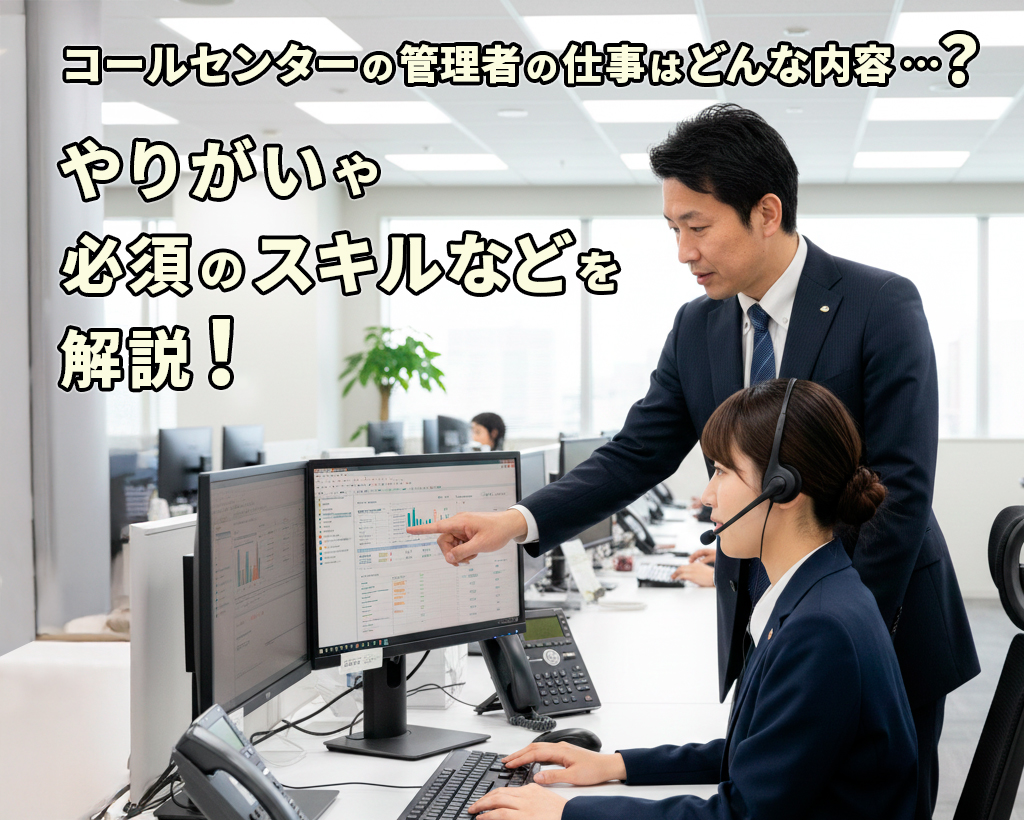「カスタマーサポート」と「コールセンター」。
どちらも顧客対応を担う部門ですが、その目的や業務内容には明確な違いが存在します。 顧客対応する部門を構築するとき、違いを理解することは部門を構築する上で不可欠です。
本記事では、カスタマーサポートとは何か、そしてコールセンターとの具体的な違いについて5つの観点から比較解説します。また、コールセンターとカスタマーセンターの違いにも触れながら、自社に適した部門の選び方や導入のポイントまでを網羅的に説明します。
すぐに試せる!小回りが効く、コールセンターシステム。
料金シュミレーション365日すぐお見積りいただけます |
14日間無料デモすぐに試せる14日間の無料デモです |
BlueBeanパートナーただいま募集中ぜひお問い合わせください |
もくじ
- カスタマーサポートの役割と主な業務内容
- コールセンターの役割と主な業務内容
- 【一覧比較】カスタマーサポートとコールセンターの5つの違い
- 自社にはどちらが最適?導入すべき部門の選び方
- 顧客満足度を高める運用成功のポイント3選
- カスタマーサポート・コールセンターを導入する5つのステップ
- 導入前に押さえておきたい3つの注意点
- まとめ
- コールセンターにも、カスタマーサポートにも!安価で柔軟に契約できるクラウド型CTIコールセンターシステム「BlueBean」
\目的に叶ったコールセンターシステムをつくれます/
カスタマーサポートの役割と主な業務内容
カスタマーサポートは、顧客が抱える問題を解決し、製品やサービスの利用を継続してもらうことで顧客満足度を高める役割を担います。
その目的は、顧客ロイヤルティの向上やLTV(顧客生涯価値)の最大化にあります。
類似する用語として、問い合わせ対応窓口を指す「ヘルプデスク」や「サポートセンター」、技術的な問題に特化した「テクニカルサポート」、能動的に顧客の成功を支援する「カスタマーサクセス」などがあり、これらは広義の「カスタマーサービス」や「カスタマーセンター」の中に含まれる機能や役割として位置づけられることがあります。
顧客が抱える問題の解決を目的とする
カスタマーサポートの中心的な役割は、顧客からのお問い合わせに対応し、直面している問題を解決することです。
オペレーターは、製品の操作方法に関する質問、サービス利用上のトラブル、料金に関するお問い合わせなど、多岐にわたる内容を受け付けます。 単に質問に答えるだけでなく、顧客の状況や背景を正確にヒアリングし、根本的な原因を特定した上で最適な解決策を提示する能力が求められます。 このプロセスを通じて顧客の不安や不満を解消し、製品や企業に対する信頼を醸成することが、継続的な関係構築の基盤となります。
お問い合わせ対応から製品の活用促進まで担当する
カスタマーサポートの業務は、顧客からのお問い合わせを待つ受動的な対応だけにとどまりません。
顧客が製品やサービスをより効果的に活用できるよう、能動的に働きかける役割も担います。
例として、新機能が追加された際にその使い方を解説するメールを配信したり、特定の機能の利用率が低い顧客に対して活用方法を個別に案内したりする活動が挙げられます。 こうした活用促進の取り組みは、顧客が製品から得られる価値を最大化させ、満足度を高めることにつながります。 結果として、サービスの解約率低下や、上位プランへの移行(アップセル)といった成果も期待できます。
BlueBean|クラウド型CTIコールセンターシステムBlueBeanでインバウンド業務を効率化
BlueBean|BlueBeanでアウトバウンド業務を効率化
コールセンターの役割と主な業務内容
コールセンターは、主に電話を通じて顧客との接点を構築し、コミュニケーションを行う部門です。
その役割は、顧客からのお問い合わせに対応するだけでなく、企業側から情報発信や販売促進活動を行うことも含みます。
電話という直接的な対話チャネルを最大限に活用することで、顧客の声をリアルタイムで収集したり、企業のブランドイメージを伝えたりできるメリットがあります。 業務内容は、インバウンド(着信)とアウトバウンド(発信)に大別され、企業の目的に応じて多様な機能を果たします。
電話応対による顧客接点の構築が目的
コールセンターの主な目的は、電話を主軸としたコミュニケーションによって顧客との接点を持ち、その関係性を構築・維持することにあります。 具体的には、顧客からの商品注文やサービスの申し込み・資料請求・各種手続きの受付など、多様な用件に対応します。
電話は、顧客の疑問や不安をその場で直接解消できるため、テキストベースのコミュニケーションよりも迅速かつ丁寧な対応が可能です。 こうした円滑なコミュニケーションを通じて、企業への信頼感や安心感を醸成し、顧客との良好な関係を築くための重要な基盤としての役割を果たします。
着信(インバウンド)と発信(アウトバウンド)の両方を行う
コールセンターの業務は、顧客からかかってくる電話を受ける「インバウンド業務」と、企業側から顧客へ電話をかける「アウトバウンド業務」の二つに分けられます。
インバウンド業務の例としては、商品やサービスに関するお問い合わせ対応・注文や予約の受付・テクニカルサポートなどが挙げられます。 アウトバウンド業務には、新商品やキャンペーンの案内・請求催促業務・市場調査やアンケートの実施・アポイントメントの獲得といったマーケティング・営業活動などの業務が挙げられます。 企業によってはどちらか一方に特化する場合もありますが、両方の機能を併せ持つことも少なくありません。
BlueBean|クラウド型CTIコールセンターシステムBlueBeanでインバウンド業務を効率化
BlueBean|BlueBeanでアウトバウンド業務を効率化
【一覧比較】カスタマーサポートとコールセンターの5つの違い
カスタマーサポートとコールセンターは、顧客と接点を持つ点で共通していますが、その本質的な役割や機能には大きな違いがあります。 両者を混同したまま部門を設計すると、期待した成果が得られない可能性があります。
ここでは、「設置する目的」「業務の方向性」「アプローチする顧客層」「活用するツールの種類」「担当者に求められるスキル」という5つの具体的な観点から、それぞれの特徴を比較し、その違いを明確にしていきます。
違い1: 設置する目的
最も根本的な違いは、部門を設置する目的にあります。
カスタマーサポートの主目的は、既存顧客が抱える問題を解決し、製品やサービスへの満足度を高めることで、継続利用を促しLTV(顧客生涯価値)を最大化することです。 問題解決を通じた顧客ロイヤルティの向上がゴールとなります。
一方、コールセンターの目的はより広範で、電話を通じたあらゆる顧客コミュニケーションを担います。 お問い合わせ対応による顧客満足度の維持はもちろん、新規顧客獲得のためのテレマーケティング、販売促進、市場調査など、営業やマーケティング活動の一環としての役割も担う点が大きな違いです。
違い2: 業務の方向性(インバウンドかアウトバウンドか)
業務の方向性においても明確な違いが見られます。
カスタマーサポートは、基本的に顧客からのお問い合わせや相談を受けてから対応を開始する「インバウンド(受動型)」業務が中心です。 顧客が何らかの課題に直面した際に、その解決を支援することが主な役割となります。
これに対してコールセンターは、インバウンド業務に加えて、企業側から顧客や見込み客へ積極的に電話をかける「アウトバウンド(能動型)」業務も行います。 新製品の案内やアンケート調査、アポイント獲得など、企業戦略に基づいて能動的にアプローチする点が特徴です。
BlueBean|クラウド型CTIコールセンターシステムBlueBeanでインバウンド業務を効率化
BlueBean|BlueBeanでアウトバウンド業務を効率化
違い3: アプローチする顧客層
対応する顧客層にも違いがあります。
カスタマーサポートが主に対象とするのは、すでに自社の製品やサービスを購入・契約している「既存顧客」です。 既存顧客がサービスを快適に使い続けられるように支援し、長期的な関係を築くことに重点を置いています。
一方、コールセンターの対象は既存顧客に限りません。
アウトバウンド業務を通じて、まだ自社の顧客ではない「見込み顧客」や「潜在顧客」にもアプローチします。 新規顧客の獲得を目指す営業活動も業務範囲に含まれるため、より幅広い層の顧客と接点を持つことになります。
違い4: 活用するツールの種類
業務内容の違いから、活用するツールの種類も異なります。
コールセンターは電話応対が業務の中心となるため、着信の振り分けや顧客情報のポップアップ表示が可能なCTIシステム、顧客管理を行うCRMシステム、応対品質向上のための通話録音システムなどが主に利用されます。
対してカスタマーサポートは、電話だけでなくメール、チャット、SNSなど複数のチャネルで対応することが多いため、これらのお問い合わせを一元管理できるお問い合わせ管理システムや、顧客の自己解決を促すFAQシステム、自動応答を行うチャットボットなどを活用する傾向があります。
違い5: 担当者に求められるスキル
担当者に求められるスキルセットも異なります。
コールセンターのオペレーターには、正しい敬語や聞き取りやすい発声といった基本的な電話応対スキルに加え、決められた時間内に効率よく対応を完了させるための処理能力が重視されます。 一方、カスタマーサポートの担当者には、基本的なコミュニケーション能力に加えて、顧客が抱える問題の背景を深く理解し、根本的な解決策を導き出すための高度な製品知識や論理的思考力、問題解決能力が不可欠です。
顧客の満足度を最大限に高めるための、より専門的なスキルが求められます。
自社にはどちらが最適?導入すべき部門の選び方
カスタマーサポートとコールセンターのそれぞれの特徴を理解した上で、自社の事業内容や目的・顧客層に合わせて最適な部門を選択することが成功の鍵となります。 既存顧客との関係性を深め、製品の継続利用を促すことが重要なのか、あるいは新規顧客の獲得を含めた顧客接点を構築したいのか。
ここでは、それぞれの導入が効果を発揮する企業の特徴を具体的に示し、自社にとってどちらの部門がより適しているかを判断するための指針を解説します。
カスタマーサポートの導入が向いている企業の特徴
カスタマーサポートの導入が特に向いているのは、SaaSやサブスクリプション型のビジネスモデルを採用している企業です。 これらの事業では、顧客にサービスを継続利用してもらうことが収益の基盤となるため、顧客満足度を高め、解約を防止する活動が極めて重要になります。
また、IT製品や専門的なソフトウェアなど、利用にある程度の知識や技術を要する商品を扱っている企業にも適しています。 顧客が直面する技術的な問題を迅速かつ的確に解決することで、製品価値を高め、顧客からの信頼を獲得できます。 既存顧客との長期的な関係構築を重視する企業に最適です。
コールセンターの導入が向いている企業の特徴
コールセンターの導入は、ECサイトやカタログ通販・金融・保険・不動産業界など、電話による注文受付・お申し込み・お問い合わせがビジネスの主要なチャネルとなっている企業に非常に有効です。
日々大量に発生する電話応対を効率的に処理する体制が不可欠な場合に適しています。
また、新商品やキャンペーンの案内を通じて積極的に販売促進を行いたい企業や、市場調査、アポイント獲得といったアウトバウンドの営業・マーケティング活動に力を入れたい企業にも向いています。 新規顧客獲得から既存顧客のサポートまで、電話を軸に幅広い顧客接点を持ちたい場合に最適です。
カスタマー
自社に合ったAIコールセンターシステムを選ぶ3つのポイント
AIコールセンターシステムやツールは数多く存在し、それぞれに特徴があります。 自社の課題解決に本当に役立つシステムを選ぶためには、いくつかの比較ポイントを押さえることが重要です。
ここでは、多くの企業向けサービスの中から自社に最適なシステムを選び出すために、注目すべき3つのポイント(機能・連携性・サポート体制)について解説します。
1. 解決したい課題に特化した機能が備わっているか
AIコールセンターシステムを選定する上で最も重要なのは、自社が抱える課題を解決できる機能が備わっているかという点です。
例えば、「オペレーターの応対品質を均一化したい」のであれば回答支援機能やAI対応。「有人対応数を削減したい」のであればFAQ最適化やチャットボット機能、AIによる一次対応代行が有効です。 まずは自社の課題を明確に定義し、その課題解決に直結する機能を持つシステムに絞って比較検討を進めることが、導入成功への近道となります。 導入目的に合っているかという観点で「最適な機能を選ぶこと」を見極める必要があります。
2. 現在使用しているシステムとスムーズに連携できるか
多くのコールセンターでは、既にCRM(顧客情報を管理するシステム)やCTI(コンピュータ・電話・FAXを連携するシステム)などの基幹システムが導入されています。 新たに導入するAIシステムがこれらの既存システムと円滑に連携できるかは、業務効率を左右する重要な要素です。
データが分断されてしまうと、二重入力の手間が発生したり、一元的な顧客情報管理ができなくなったりします。 API連携の可否や連携実績などを事前に確認しましょう。
3. 導入後のサポートやメンテナンス体制は整っているか
AIシステムは導入したら終わりではなく、その効果を最大限に引き出すためには、継続的な運用と改善が欠かせません。
そのため、導入ベンダーのサポート体制が充実しているかは重要です。 導入時の初期設定支援はもちろん、運用開始後のレポーティングや効果測定、AIの学習データ追加や精度チューニングに関するアドバイスなど、伴走型のサポートを提供してくれる企業・サービスを選んだ方がいいでしょう。
万が一のトラブル発生時に迅速に対応してくれるかどうかも含め、長期的な視点でパートナーとして信頼できるかを見極めましょう。
カスタマーサポート・コールセンターを導入する5つのステップ
カスタマーサポートやコールセンターを成功裏に導入するためには、場当たり的な対応ではなく、戦略的かつ段階的なアプローチが求められます。
なぜこの部門が必要なのかという目的の明確化から始まり、具体的な業務プロセスの設計・ツールの選定・人材の確保と育成・応対品質を担保するマニュアル作成まで、一連のプロセスを着実に進めることが重要です。 ここでは、導入を円滑に進めるための具体的な5つのステップについて、それぞれの段階で押さえるべきポイントを解説します。
ステップ1: 現状の課題と導入目的を明確にする
導入を検討する最初のステップは、自社が現在抱えている課題を具体的に洗い出し「それらを解決するために何を達成したいのか」導入の目的を明確にすることです。
「お問い合わせへの返信に時間がかかりすぎている」「顧客からのクレームが多い」「見込み客へのアプローチができていない」など、現状の問題点をリストアップします。 その上で、「平均応答速度を○分以内に短縮する」「顧客満足度を○%向上させる」「月間のアポイント獲得件数を○件にする」といった、定量的・定性的な目標を設定します。 この目的が、今後のすべての意思決定の土台となります。
ステップ2: 具体的な業務プロセスを設計する
設定した目的に基づき、顧客対応の具体的な業務プロセスを設計します。
対応チャネル(電話・メール・チャット等)の選定、受付時間、担当者の役割分担、お問い合わせ内容に応じた対応フローなどを詳細に決定します。
特に、一次対応で解決できない複雑なお問い合わせを、専門知識を持つ担当者や他部署へスムーズに引き継ぐためのエスカレーションルールを明確に定めておくことが重要です。 フローチャートなどを用いて業務の流れを可視化することで、担当者間の認識のズレを防ぎ、業務の標準化を図ります。 これにより、属人化を避け、安定した運用が可能になります。
ステップ3: 必要なツールやシステムを選定する
設計した業務プロセスを効率的に実現するためのツールやシステムを選定します。
コールセンターであればCTIシステムやCRM、カスタマーサポートであればお問い合わせ管理システムやFAQシステムなどが主な候補となります。
ツール選定の際は、自社の事業規模や予算、必要な機能を満たしているかを慎重に評価します。 また、将来の組織拡大やお問い合わせ件数の増加にも対応できる拡張性があるか、すでに社内で利用している他のシステムと連携できるかといった点も重要な検討項目です。 複数のサービスを比較し、無料トライアルなどを活用して実際の操作性を確認することが推奨されます。
ステップ4: 担当者の採用や教育制度を整備する
部門を実際に運営する人材の採用と育成計画を立てます。
求める人物像や必要なスキル(コミュニケーション能力・PCスキル・問題解決能力など)を明確にした上で採用活動を行います。
採用後は、担当者が自信を持って業務に取り組めるよう、充実した教育制度を整備することが不可欠です。 製品知識・業務フロー・システムの操作方法・ビジネスマナーといった基礎研修はもちろん、先輩社員とのOJTやロールプレイングを通じて実践的なスキルを磨く機会を設けます。 継続的な学習を支援する仕組みを構築し、チーム全体のスキルアップを図ります。
ステップ5: 応対品質を均一化するマニュアルを作成する
担当者による応対品質のばらつきを防ぎ、誰が対応しても一定水準以上のサービスを提供できるように、詳細な業務マニュアルを作成します。 マニュアルには、基本的な応対フロー・言葉遣いのルール・よくある質問と回答例(FAQ)・クレームや緊急時などのイレギュラー対応手順・エスカレーションの基準などを網羅的に記載します。
担当者が業務中に疑問や不安を感じた際に、すぐに参照して自己解決できるような、分かりやすく検索しやすい構成を心掛けることが重要です。 マニュアルは定期的に見直し、新しい情報や変化する状況に合わせて更新し続ける必要があります。
導入前に押さえておきたい3つの注意点
カスタマーサポートやコールセンターの導入は、顧客満足度の向上や業務効率化など多くのメリットをもたらしますが、計画段階で見落としてはならない注意点も存在します。 導入コストや運用体制、継続的な改善の必要性などを事前に十分に理解しておかないと、導入後に想定外の問題に直面する可能性があります。
ここでは、導入を検討する際に必ず念頭に置いておくべき3つの重要な注意点について、具体的に解説します。
注意点1: 導入時と運用時にそれぞれコストがかかる
顧客対応部門の立ち上げには、初期費用である導入コストと、継続的に発生する運用コストの両方が必要です。
導入コストには、CTIやCRMといったシステムの導入費用、パソコンやヘッドセットなどのハードウェア購入費、オフィスの賃料や内装工事費などが含まれます。 一方、運用コストの大部分を占めるのが担当者の人件費であり、その他にシステムの月額利用料や通信費などもかかります。 特に人件費は大きな負担となるため、必要な人員数を正確に見積もり、全体の予算計画を慎重に立てることが不可欠です。
注意点2: 安定した通信環境の整備が必須となる
特にクラウド型のシステムを利用する場合や、電話応対が業務の中心となる場合、安定した高速なインターネット通信環境は業務品質を支える生命線です。
通信が不安定だと、通話音声の途切れやシステムのフリーズといったトラブルが発生し、顧客に不快感を与えるだけでなく、業務効率を著しく低下させる原因となります。 十分な通信帯域を確保した回線契約や、信頼性の高いプロバイダの選定が重要です。 また、在宅勤務を導入する場合は、従業員各自の自宅における通信環境の基準を設け、その整備を支援するなどの配慮も必要になります。
注意点3: 顧客の視点に立った改善を継続的に行う
顧客対応部門は、一度構築したら完成というわけではありません。
市場の環境や顧客のニーズは絶えず変化するため、その変化に対応し、常に最高のサービスを提供し続けるためには、継続的な改善活動が不可欠です。 応答率や解決率といったKPIを定めて定期的にパフォーマンスを測定したり、顧客満足度アンケートを実施してフィードバックを収集したりすることで、課題を客観的に把握します。 そして、その課題を基に業務プロセスやマニュアルを見直し、改善していくPDCAサイクルを回し続ける姿勢が求められます。
まとめ
カスタマーサポートとコールセンターはどちらも企業にとって重要な顧客接点ですが、その目的と役割には明確な違いがあります。
カスタマーサポートは既存顧客の問題解決を通じてLTV向上を目指す一方、コールセンターは電話を主軸にインバウンドとアウトバウンドの両面から幅広い顧客コミュニケーションを担います。 自社のビジネスモデルや課題、目的を明確にし、どちらの機能がより適しているかを判断することが重要です。 適切な部門を選択し、計画的なステップで導入を進め、運用開始後も継続的な改善を行うことで、顧客満足度を高め、企業の成長に貢献する強力な部門を構築できます。
コールセンターにも、カスタマーサポートにも!安価で柔軟に契約できるクラウド型CTIコールセンターシステム「BlueBean」
クラウド型CTIコールセンターシステム「BlueBean」は、コールセンター業務とカスタマーサポート業務の双方に対応できる多彩な機能を搭載しています。
クラウドサービスであるため、インターネット環境があれば場所を問わずに利用でき、在宅勤務や分散拠点での運用にも柔軟に対応可能です。 着信時に顧客情報をPC画面に表示するポップアップ機能や全通話録音、IVR(自動音声応答)といったCTIの基本機能はもちろん、CRMとの連携もスムーズに行えます。 これにより、顧客情報の一元管理を実現し、どの担当者が対応しても一貫性のある高品質な顧客体験の提供を支援します。