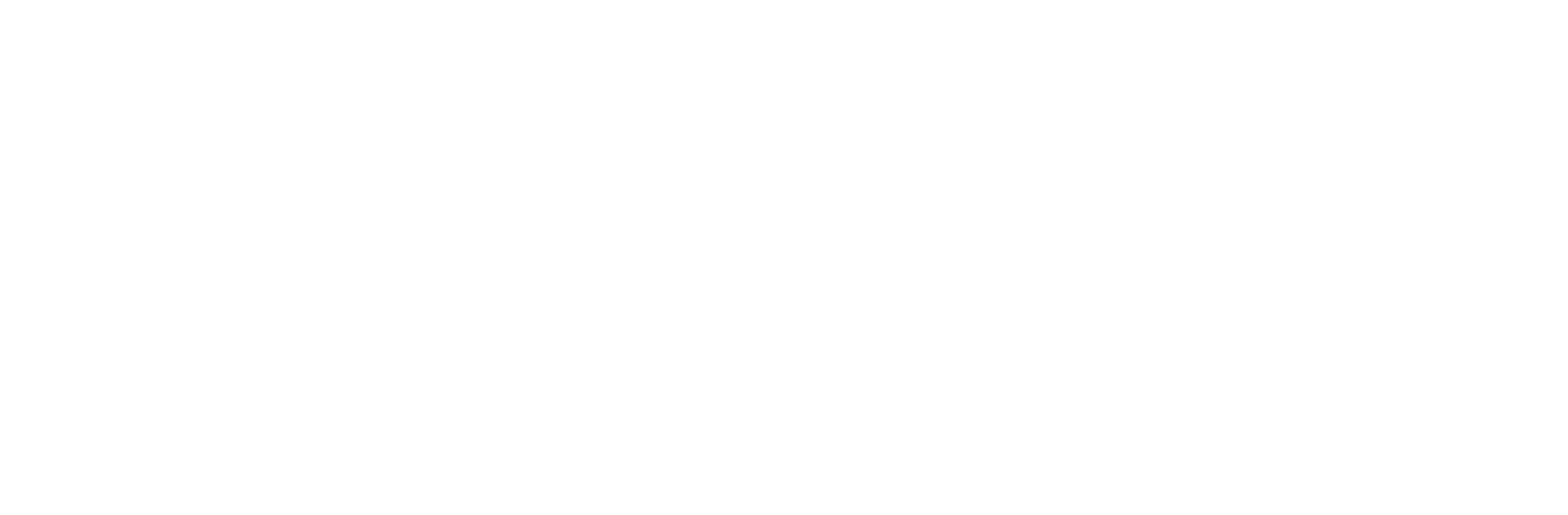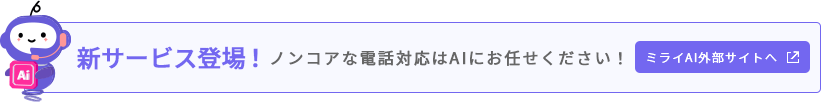コールセンターの運営において重要な課題のひとつ、「溢れ呼(あふれこ)」。
溢れ呼とは、コールセンターの対応可能な電話回線数やオペレーターの人数を超えて入電が殺到し、顧客からの電話が繋がらない状態を指します。電話が「あふれて」しまうこの状況は、顧客満足度の低下や機会損失に直結しかねません。
溢れ呼が発生する原因を理解し適切な対策を講じることが、コールセンターの品質向上には不可欠です。本記事では、溢れ呼の基本的な知識から、具体的な解決策までを詳しく解説していきます。
本記事では、カスタマーハラスメントの現状や影響、さらにコールセンターで実践できる具体的なカスハラ対策について解説します。
まずは基本から!溢れ呼の定義を解説
「溢れ呼」の読み方は「あふれこ」であり、その意味はコールセンターの受電能力を超過した着信のことです。
具体的には、用意された電話回線の数や対応可能なオペレーターの人数を上回る電話が同時にかかってきた結果、顧客が電話をかけても話し中になったり、自動的に切断されたりする状態を指します。
溢れ呼とは、システム上、着信そのものが受け付けられない状態であり、顧客にとっては企業との接点を持つことさえできない状況を意味します。 つまり、溢れ呼とは、企業の機会損失に直接つながる深刻な問題と言えます。
溢れ呼と混同しやすい「放棄呼」「待ち呼」との違い
溢れ呼と似た用語に「放棄呼」と「待ち呼」が存在し、それぞれ意味が異なります。 溢れ呼は、コールセンターの回線数自体を超えた入電で、システムが着信を拒否し、顧客側では話し中になる状態です。
一方「待ち呼」は回線には繋がったものの、オペレーターが全員対応中のため、順番待ちをしている状態の呼を指します。 そして「放棄呼」は、この待ち呼の状態でオペレーターに繋がる前に顧客が待ちきれずに電話を切断してしまった呼のことです。
溢れ呼は顧客が企業とまったく接点を持てないのに対し、放棄呼は一度は繋がったものの待たされた結果、顧客体験を損なう点で異なります。 これらの指標を正しく区別して把握することが、センターの課題分析には不可欠です。
なぜ電話が繋がらない?コールセンターで溢れ呼が起こる3つの主な原因
溢れ呼が発生する背景には、いくつかの典型的な原因が存在します。
これらを正確に把握することが、効果的なあふれ呼対応の第一歩となります。
主な原因としては、特定の時間帯や時期に問い合わせが殺到する「入電の集中」、そもそも問い合わせ件数に対して「オペレーターの人数が不足している」こと、そして顧客が自ら疑問を解決できる「WebサイトやFAQが不十分」であることなどが挙げられます。 これらの要因が単独または複合的に絡み合うことで、コールセンターの処理能力を超えてしまうのです。
原因1:キャンペーンや休日明けなど特定の時期に入電が集中する
コールセンターへの入電は常に一定ではなく、特定の時期や時間帯に集中する傾向があります。
例えば、新商品やサービスのキャンペーン開始直後、テレビCMの放映後または休日明けの午前中などは、問い合わせが急増し溢れ呼が発生しやすくなります。
このような予測可能な入電のピークに対して、オペレーターのシフト調整や人員配置が追いつかないことが直接的な原因です。 特に、短期間の急激な問い合わせ増に対応するために常に最大数の人員を確保しておくことは、コスト面から現実的ではありません。
そのため、ピーク時の問い合わせを平準化したり、あふれ呼ivrのようなシステムで一部の対応を自動化したりする仕組み作りが求められます。
原因2:オペレーターの人数が問い合わせ件数に対して不足している
恒常的なオペレーター不足は、溢れ呼を引き起こす根本的な原因のひとつです。
予測される問い合わせ件数に対して、対応可能なオペレーターの人数が慢性的に足りていない場合、日常的に電話が繋がりにくい状況が発生します。
この問題は、単に在籍人数が少ないことだけが原因ではありません。
例えば、新人オペレーターが多く、一人当たりの応対時間(AHT)が長引いてしまう場合も、実質的なリソース不足に陥ります。
また、高い離職率によって安定した人員確保が難しい状況も、溢れ呼の発生に繋がります。 入電予測の精度が低く、適切な人員配置計画(WFM)ができていないケースも、時間帯によっては深刻なオペレーター不足を招く要因となります。
原因3:WebサイトやFAQで顧客が自己解決できない
多くの顧客は、電話で問い合わせる前に、まず企業のWebサイトやFAQページで情報を探し、自己解決を試みます。
しかし、その自己解決のチャネルが十分に機能していない場合、本来は電話を必要としない簡単な質問までコールセンターに集中してしまいます。
例えば、「FAQの情報が古い」「知りたい情報が見つけにくい」「そもそも必要な情報が掲載されていない」といった状況です。
このような簡単な問い合わせが電話に流入することで、オペレーターのリソースが圧迫され、緊急性の高い、あるいは複雑な問題を抱えた顧客からの電話が繋がりにくくなるという悪循環を生み出します。
結果として、コールセンター全体の処理能力を超え、溢れ呼を発生させる一因となるのです。
溢れ呼の放置は危険!企業が被る3つのデメリット
溢れ呼を「単に電話が繋がらないだけ」と軽視することは危険です。
企業の評判や収益に深刻な悪影響をおよぼす可能性があります。
具体的には、顧客体験を損なうことによる「顧客満足度の低下」、製品購入やサービス契約の機会を逃す「機会損失」、そして繋がらない電話に対応できないことから生じる「オペレーターの負担増加」という、3つの大きなデメリットが考えられます。
これらの問題は互いに影響し合い、企業の成長を阻害する要因となりかねません。
デメリット1:顧客満足度が低下し企業に対する信頼性を損なう
顧客にとって、問題を解決したい」あるいは情報を得たいときに電話が全く繋がらない状況は、大きなストレスとなります。特に緊急の用件やトラブルに関する問い合わせの場合、繋がらないことで顧客の不安や不満は増大し、企業に対する信頼を大きく損なうこととなります。
このようなネガティブな体験は顧客満足度の著しい低下に直結し、最悪の場合、サービス解約や他社への乗り換えといった顧客離れを引き起こす原因となります。
また、商品購入を検討している新規顧客からの問い合わせが溢れ呼となった場合、最初の接点で悪い印象を与えてしまいます。結果として、得られたはずのビジネスチャンスをみすみす逃すことにもなります。
デメリット2:売上減少に直結する機会損失が発生する
溢れ呼は、具体的な売上の機会損失に直接的に結びつきます。
例えば、商品の注文やサービスの申し込みを電話で受け付けている場合、その電話が繋がらなければ、顧客は購入を諦めてしまうか、より簡単に繋がる競合他社の製品を選んでしまう可能性が高いです。
これは、得られるはずだった売上がゼロになることを意味します。
また、既存顧客からの問い合わせであっても、関連商品や上位プランを提案するアップセル・クロスセルの機会を失うことにも繋がります。
1件あたりの損失は小さく見えても、溢れ呼が常態化しているコールセンターでは、年間を通じて見ると莫大な金額の機会損失が発生している可能性があります。経営上の大きな課題となります。
デメリット3:オペレーターの業務負担が増え離職率が悪化する
溢れ呼は、顧客だけでなく、現場で働くオペレーターにも大きな負担を強います。常に電話が鳴り続けて対応しても待っている顧客がいるという状況は、オペレーターに絶え間ないプレッシャーを与え、精神的にも肉体的にも疲弊させます。
さらに、長時間待たされたことで不満を募らせた顧客から、電話が繋がらないこと自体へのクレームを受けることも少なくありません。こうしたストレスの多い労働環境は、オペレーターのモチベーションを著しく低下させ、バーンアウト(燃え尽き症候群)などを引き起こし、最終的には離職率の悪化に繋がります。
離職者が増えると、残されたオペレーターの負担はさらに増し、新人採用や教育のコストもかさむという負のスパイラルに陥ってしまいます。
溢れ呼を解消するための効果的な対策5選
溢れ呼がもたらすデメリットを回避するためには、具体的な対策を講じる必要があります。
対策のアプローチは多岐にわたり、ITシステムを導入して業務を自動化・効率化する方法や、顧客の行動を変えて入電自体を減らす方法などがあります。自社のコールセンターが抱える課題や規模に応じて、これらの対策を単独または組み合わせて実施することが効果的です。
ここでは、溢れ呼を解消するために有効な5つの具体的な対策を紹介します。
対策1:IVR(音声自動応答システム)で問い合わせ内容に応じて電話を振り分ける
IVR(音声自動応答システム)は、呼対策の基本的な手段のひとつです。
顧客からの着信時に自動音声ガイダンスを流し、プッシュ操作によって問い合わせ内容を振り分ける仕組みです。
例えば「新規申し込みの方は1番」「契約内容の確認は2番」のように誘導することで、適切なスキルを持つオペレーターや専門部署に直接電話を繋ぐことができます。これにより、無駄な取り次ぎ時間が削減され、応対効率が向上します。
また、よくある質問に対しては、音声ガイダンスのみで回答を完結させることも可能です。
営業時間外にはWebサイトのFAQへ誘導したり、翌営業日のコールバック予約を受け付けたりする機能もあり、オペレーターが対応できない時間帯の顧客満足度低下を防ぐ役割も果たします。
対策2:チャットボットやFAQコンテンツを充実させ自己解決を促す
コールセンターへの入電数を抑制し、溢れ呼の根本原因を解消するためには、顧客の自己解決を促進する環境作りが極めて重要です。
その中心となるのが、Webサイト上のFAQコンテンツの充実です。
顧客が抱える疑問の多くはよくある質問で解決できるため、FAQを網羅的かつ分かりやすく整備することで、電話での問い合わせを大幅に削減できます。探しやすさを向上させるための検索機能の強化や、直感的なカテゴリ分類も欠かせません。
さらに、24時間365日対応可能なチャットボットを導入すれば、顧客は時間や場所を問わずに気軽に質問でき、自己解決率は一層高まります。
対策3:ボイスボット(AI電話自動応答)で一次対応を自動化する
ボイスボット(AI電話自動応答)は、AI技術を活用して音声での問い合わせに自動で対応するシステムです。
従来のIVRがプッシュ操作を基本とするのに対し、ボイスボットは顧客が話す自然な言葉を認識し、対話形式で応答できる点が大きな特徴です。 これにより、資料請求や来店予約の受付、定型的な質問への回答といった一次対応を完全に自動化することが可能になります。 ボイスボットがこれらの用件を処理することで、オペレーターは人でなければ対応できない複雑な相談やクレーム対応に集中できます。
結果として、コールセンター全体の生産性が向上し、入電集中時でも溢れ呼を発生させにくくなります。
24時間365日稼働できるため、営業時間外の顧客対応も実現できます。
対策4:コールバック予約を導入し顧客の待ち時間をなくす
コールバック予約は、電話が混み合っている際に顧客が長時間待たされるのを防ぐ有効な手段です。
このシステムは、WebサイトやIVRを通じて、顧客が自分の電話番号と希望する時間帯を登録すると、後でオペレーターから折り返し連絡するという仕組みです。
顧客にとっては、保留音を聞きながら電話口で待ち続けるストレスから解放される大きなメリットがあります。一方、企業側にとっては、待ちきれずに電話を切られてしまう「放棄呼」を減らし、機会損失を防ぐことができます。さらに、コールセンター側は、問い合わせが比較的少ない時間帯を見計らって折り返し対応を行うことで、業務負荷を平準化する効果も期待できます。
顧客満足度を維持しながら、入電ピーク時の負担を軽減する現実的な対策です。
対策5:外部のコールセンター(アウトソーシング)に業務を委託する
自社内でのリソース確保が難しい場合、コールセンター業務の一部または全部を外部の専門業者に委託するアウトソーシングも有効な選択肢です。
専門業者は、コールセンター運営の豊富なノウハウや教育済みのオペレーター、最新のシステムを保有しているため、迅速に高品質な応対体制を構築できます。これにより、自社でオペレーターを採用・育成するコストや時間を大幅に削減可能です。
特に、キャンペーン期間中など一時的に入電が急増する際に、その期間だけ業務を委託すれば、柔軟に繁閑の差に対応できます。一次対応のみ、あるいは夜間・休日のみといった特定の業務範囲を切り出して委託することも、溢れ呼対策として効果的です。
ただし、委託コストや情報漏洩リスク、応対品質の管理といった点を考慮し、信頼できるパートナーを慎重に選定することが求められます。
溢れ呼の対策を一挙に解決CTIコールセンターシステム「BlueBean」
これまで紹介した溢れ呼対策の多くは、高機能なコールセンターシステムを導入することで効率的に実現できます。
クラウド型CTIコールセンターシステム「BlueBean」は、溢れ呼対策に有効な機能を標準で数多く搭載しています。
例えば、問い合わせ内容に応じて着信を自動で振り分けるIVR機能や、オペレーターの対応状況をリアルタイムで可視化するモニタリング機能、放棄呼や待ち呼の発生状況を分析できるレポート機能などが、コールセンターの現状把握と改善に役立ちます。
クラウドサービスであるため、大規模な設備投資は不要で料金も日割りで計算。契約における縛り期間もなし。短期間かつ低コストで導入を開始できる点も特徴です。
溢れ呼をはじめとするコールセンターの様々な課題を、ひとつのシステムで包括的に解決へと導きます。
また、人手不足でおなやみであれば、溢れ呼時の一次対応をAIが代行する「BlueBean AI」もお力になれます。
*BlueBean AIのご活用方法をこちらで紹介しています。
まとめ
溢れ呼は、コールセンターにおける単なる技術的な問題ではなく、顧客満足度の低下、機会損失、オペレーターの離職率悪化といった経営課題に直結する重要な指標です。
その発生原因は、キャンペーンなどによる一時的な入電集中から、恒常的なオペレーター不足、WebサイトのFAQが不十分であることまで多岐にわたります。
これらの課題を解決するためには、IVRやボイスボットによる対応の自動化、FAQやチャットボットによる自己解決の促進、コールバック予約による顧客の待ち時間削減といった、多角的なアプローチが求められます。
自社のコールセンターの現状を各種データに基づいて正確に分析し、原因に応じた適切な対策を計画的に実行していくことが、溢れ呼の発生を抑制し、応対品質を向上させるための鍵となります。